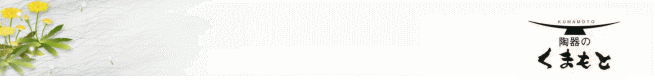 |
||
| 日本芸術院会員と重要無形文化財保持者 | ||
| 陶芸を極めると行き着くところは何処なのか。 その答えは、作家の志す方向によって二通り考えられます。 芸術家として独自の境地の確立を目指す人と、 職人として作陶技術の完成度の高さを追及する道を歩む人です。 それぞれの道に客観的な評価基準となる道標が用意されています。 芸術家の場合は日展、そして職人の場合は日本工芸会です。 その最高峰が日展の場合 日本芸術院会員で、 日本工芸会の場合 重要無形文化財保持者ということになります。 その趣旨からも、また過去の歴史からも両者を兼ねることは在りません。 |
||
| エピソード 青木龍山氏が日本芸術院会員になられた平成4年のある祝賀会でのことです。 議員の方が龍山氏の側に歩み寄られて 「先生、この度は日本芸術院会員ご就任おめでとうごいます。 つぎはいよい人間国宝(重要無形文化財保持者の通称)ですね!?」 褒章、栄誉等には精通されておられる筈の議員の先生をしてこのご発言です。 一般的な日本芸術院会員の認知度も推して知るべしといったところではないでしょうか。 |
||
| すべての作家にとって最高の栄誉である文化勲章。 陶芸家では、これまで日本芸術院会員の方が三名、 そして重要無形文化財保持者の方が三名受賞されております。 ただ、昭和46年の荒川豊蔵氏を最後に三十年近く 重要無形文化財保持者からの受賞者はいらっしゃいません。 また、制度上も文化功労者の中から文化勲章受賞者が決定されるようになりましたが、 変更後顕彰された陶芸の文化功労者はすべて日本芸術院会員の方で占められています。 文化勲章受章者の作品評価は、それ以前と比べて飛躍的に高まります。 その最も近くに位置していらっしゃるのが青木龍山氏であることに異論を唱える余地はないと思います。 ※平成17年10月28日文化勲章を受章されました。 |
||
| エピソード 平成8年佐賀県有田町で炎の博覧会が開催された時のことです。 このメイン会場の展示は素晴らしいもので、 その時点までのすべての日本芸術院会員8名と 重要無形文化財保持者27名(総合指定三団体を含む) の作品を各二点ずつ展示してありました。 佐賀県はそれを記録に残すべく図録を作成したのですが、 その原稿を当時の通産省に提出したところ、 一ヶ所の訂正を回答してきました。 原稿では重要無形文化財保持者・日本芸術院会員と掲載されていたのですが、 日本芸術院会員を先にするように、との事だったようです。 掲載順位にどれほどの意味があるのかは判りませんが、 少なくとも中央官庁レベルでは、日本芸術院会員が優先されることになっているようです。 |
||